■ コラム ■
2005年1月から2008年3月までのの記事がご覧になれます。
第10回Human & Social サイエンス・カフェ
2008年3月2日(日)
テーマ:「ブッシュ外交の総括―「対テロ戦争」の8年」 講師:平田雅己准教授
以前から耳にしておりましたサイエンスカフェに参加しました。今回は、昨年春に私が受講させていただいた、平田先生のスピーチでしたので背中をぐっと押され参加しました。演題はブッシュ外交の評価という、大統領選挙に沸くアメリカ外交の実態という、今を旬とするテーマで大変興味がそそられました。
常に事実の積み重ねによる歴史的事件の検証、またそれに至った決断の真相にせまるという平田先生の手法は,大変おもしろく楽しませていただきました。今回の副題であるイラク戦争の政策、という世界が注目しているテーマも事実を積み重ねていただき、ホントかよ、といいたくなるような事実でした。
私見でありますが、アメリカという国は移民国家ではありますが、基本的に白人中心の発想を持った政策を進める国でもあり、自分のスタンダードに合わない、またどんな分野でも自国より少しでも優越的地位にある国が出てくると、敵愾心をむき出しにするという競争国家でもあります。しかしこの国は、必ずどこかで振り子が戻る国でもあり、先生の説明にもありましたチャーチルの言ったとうりの国でもあります。日本政治ではありえない、やれば立ち上がることが出来ないほどの袋叩きに合うのは必定。
平田先生のスピーチはこれらの政治状況の中で、誰がそのときどのように行動し、どんな発言をしたか、具体的に示していただき、当該人物の職歴などからも説得性のあるものでした。時々スピーチは主題とは違ったわき道に入るのですが、歴史の面白さはこのまったく違う角度から見てみるという、これが大切といつも思っております。シンディシーハンに事例がそうです。ほんのささいなことがその後の政治に大きな影響を与えたことは多くあります。歴史検証の醍醐味でもあります。
大西 聰(参加者)
第9回Human & Social サイエンス・カフェ
2008年2月17日(日)
テーマ:「少年犯罪」 講師:山田美香准教授


第8回Human & Social サイエンス・カフェ 2008年1月27日(日)
テーマ:「途上の言語―イタリア・ピエモンテ地方のオック語への旅」
講師:佐野直子准教授
 以前から会の活動は知っていましたが、今回のタイトルに引かれ初めて参加しました。私たちが毎日何気なく、あるいは意識して使っている言語が、人間の生活や文
化、歴史にどれほど重要かと、益々強く思うようになっているからです。
イタリアの山岳地帯の少数派言語、オック語の成り立ちから変遷、現在の状況などをお聞きしました。佐野先生が現地取材の際、日本人女性が何しにこんな辺鄙な場所
に来たのかと怪しまられた時、オック語の歌を一緒に歌って、一気に疑いが晴れたことなど、言葉がいかに人と人の関係を繋げるものかと実感。最近、若者たちでオック
語の歌詞で音楽を作るのが流行し、CDで少し聴かせてもらいましたが、時間があれば1曲聴きたかったくらい。で、日本でもこの数年、沖縄の言語を取り入れた曲が人気
を呼んでいるのと同じような現象ではと、面白く思いました。
以前から会の活動は知っていましたが、今回のタイトルに引かれ初めて参加しました。私たちが毎日何気なく、あるいは意識して使っている言語が、人間の生活や文
化、歴史にどれほど重要かと、益々強く思うようになっているからです。
イタリアの山岳地帯の少数派言語、オック語の成り立ちから変遷、現在の状況などをお聞きしました。佐野先生が現地取材の際、日本人女性が何しにこんな辺鄙な場所
に来たのかと怪しまられた時、オック語の歌を一緒に歌って、一気に疑いが晴れたことなど、言葉がいかに人と人の関係を繋げるものかと実感。最近、若者たちでオック
語の歌詞で音楽を作るのが流行し、CDで少し聴かせてもらいましたが、時間があれば1曲聴きたかったくらい。で、日本でもこの数年、沖縄の言語を取り入れた曲が人気
を呼んでいるのと同じような現象ではと、面白く思いました。
イタリアでは「言語的少数派保護法(482法)」(1999年)が制定され、オック語など少数派言語が明記され、補助金もどんどん出され、保護する運動が広 がったものの、さまざまな問題点もあると話されました。ひょっとしたらこのオック語って何百、千?年後の日本語に通じるかも、と身近に考えてしまいました。今、世 界の少数言語がどんどん消えていく中、日本語を話すのは日本だけ。「多文化・多言語主義」に賛成ですが、では狭い地域でしか使われない言語をどう活用し、残してい くかとなると、正直わかりません。「世界遺産」として自然や街並みが保護され、こういうものは貴重だと世界の人たちに認識されていますが、少数言語も同じよ うに大事なものだと思います。
2時間があっという間でした。この先、オック語がどうなるか気になり、「地域によってバラバラなオック語を一つに統一してきちっとした言語にしたら残るのでは」 と帰りがけに先生に話しかけてしまいました。「無理に統一を図らず、オック語を使う人々が、ああだ、こうだとどうしたらいいかと繰り返し議論し続けることが、この 言語が生命力を保つエネルギーになるでしょう」と返して頂きました。ありがとうございました。 (白石)
第7回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年12月16日(日)
テーマ:「アメリカ文学のニューオーリンズ」
講師:田中敬子教授
わかりやすく、楽しく参加できてよかったと、感謝していま
す。ニューオーリンズという地名は、なんとなくなじみがあり、 (音楽の関係か?)アメリカ文学の中では多くの作品の舞台に なっていると思い込んでいましたが、案外に少ないのだなとい
う印象です。(フォスターなどの歌の舞台もあの辺と思いこん
でいました。)
一国の文学などを論議するときには、当然、その国の歴史や
地理、時代背景、社会背景、等の基礎知識が必要となりますが
、配布資料を見ていて、自分が特に、地理面・アメリカ開拓史
(ニュオーリンズの歴史)においてうとかったかということを
再認識しました。
お話をきいているうちに自分の場合、映画を見て、アメリカ
の文学像を構成している可能性も高いということも気がつい
て
きました。
田中先生の聴講生からの質問に対する懇切な、ある意味ではやさしさを感じさせる対応には敬服するとともに、時間配分として十分に質疑の時間をとられていることで、参加者として安心して、質問の手を上げることができたことを申し添えます。 参加者 藤田吉長
第11回 マンデーサロン
2007年12月10日
山田陽子さん 「満州泰阜分村−70年の歴史と記憶 ―歴史から学ぶこと―」
山田さんは自分が編集委員として刊行された本『満州泰阜分村―70年の歴史と記憶』をもとに「歴史から学ぶこと」をテーマとして報告しました。報告は泰阜分村大八浪開拓団の旧満洲への入植、開拓団員の生活、終戦後の残留、そして日中国交正常化後に帰国した人たちに対して泰阜村が行った定着自立支援などについて詳細な説明が行われました。今度の報告を通して、私は初めて日本国民も被害者だという事実を深刻に認識し、当時の開拓団員の生活に関心を持つようになりました。報告によると終戦後、中国東北部の中国の住民は、戦い合った立場を超えて残留した日本人を受け入れ、助けました。戦争という残酷な歴史の中で、こういう人たちは既に日中友好の種を撒き始めたということに一番感動しました。また、満洲分村移民を送り出した責任主体として小さな泰阜村の堂々たる責任を引き受ける姿勢にも感心しました。
一言で言えば、今度の山田さんの報告は日本と中国との国際交流を深く考えさせる内容でした。山田さんの声がとてもきれいだったので、内容が重い報告でしたが、その声に参加者の皆さんは魅惑されたようです。私と山田さんは同じく成田先生の下で研究しているので、この本を完成するために、山田さんが何度も中国に行ってかなり詳細な研究を行ったことは知っております。『満洲泰阜分村―70年の歴史と記憶』は泰阜村の村史として刊行されましたが、泰阜村の歴史を通して日本と中国双方の歴史全般を覗くことができるし、日中友好の促進にも意義深いものだと思われます。そして、中国残留者問題への日本社会の注目を集め、戦争が残した問題の解決を促進する面でも大きな意義があると思われます。
朴香花(博士前期課程)
宮本佳範さん 「H・ヨナスの思想に基づく自然保護教育」
この度、初めてマンデーサロンに参加いたしました。宮本さんの「H・ヨナスの思想に基づく自然保護教育」論は、現在の環境ブームの風潮に自然保護教育の在り方を再考する提言として意義深いものでした。実は、私は宮本さんと同じゼミに所属していますので、宮本論の構築を傍で拝見しております。ゼミではヨナスの思想をはじめとする様々な思想を分かりやすい比喩を用い、口調は穏やかながらも熱く語る姿が印象的です。
今回は、「自然と触れ合うこと=自然保護教育」ではなく、自然保護につながる教育となりうるという根拠を理論的に考えていくひとつの例示という主旨でした。最後に、宮本さんの受賞式のスライドが数枚紹介されました。受賞記念品の紹介もあり、飾るに飾れないとのことで押入れに眠っているとのこと。その話で、それまでの難解な話から一気に和やかな雰囲気に包まれました。
発表者と参加者とが一体となってその場の空気を形作るようなあっという間の2時間でした。院生の参加は少ないようですが、自分の研究領域以外の発表は目から鱗の新鮮さがあります。毎月開催されているようですので、どうぞ皆様も一度参加されることをお勧めいたします。
大野裕美(博士前期課程)
第6回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年11月18日(日)
テーマ:「血液型性格論のホントのトコロ」
講師:久保田健市(人間文化研究科准教授)

まずはこのような機会を見つけ、参加できたことがうれしかったです。自分が社会人になってから、2部の大学へ通っていた頃の、他の大人たちと一緒に何かを学んだり考えたりする空気に触れた気がして、始まるまでの緊張感と好奇心とでうれしくて仕方ありませんでした。とても楽しく2時間が過ぎていきました。時間があっという間に過ぎてしまってので、他の参加者の意見や感想などの交流する時間が少なくなってしまったことが残念でした。
血液型性格論というところでは、自分自身仕事の関係で一緒になった人としゃべっていて血液型の話になると、漠然とこうかなと思うとあたることが多々あるため、実際のところの何か因果関係があるのではないかと考えるようになりました。ただ、なぜその血液型はそうなのか、具体的に考えていくと生物学的なところに入っていき、血液と脳のそれぞれの機能と関連など、知らないことが多すぎて想像することもできません。そうしたときに
、そもそも血液型ABOの分類自体について、血液の種類は4つの種類があると思っていたけれど、そう考えるのではなく「Aか、Bか、AとB両方あるのか、AとBどちらともないのか」と、すべての血液は、2種類の4分類と考えるんじゃないかと。
そう考えたときに、すべての血液を2種類の4分類したものに対して、性格も同じように、すべての性格を2種類の4分類したうえで、血液型と性格との相関関係を考えなくてはいけないとすると、ではその性格の定義はなにか?というところが大事なのではないかと。そして性格をどう計るのかという問題も考えられます。 結局本人としては自分の性格をこう思っているけれど、周りから見たら「あなたこうでしょう」という
ところは十分考えられ、その周りの人の意識についてもその人がどうゆう性格意識をもっていて何と比較してその本人に「あなたはこうでしょう」と思ったか、までを含めて考えないと性格をうまく計ることが難しいといえるのではないかと。
ただそうまでして血液型と性格をつなげて、意味があるのかと考えると、結局ふだんの会話のネタ程度ぐらいしか意味がないかと思うと探究心も萎えてしまいます。逆に今回の話であったように、それによる差別や偏見などにつながるなら、そのままブラックボックスのまま「当たるときもあれば、はずれるときもある」でいいのかなと思いました。 服部 正(参加者)
第10回 マンデーサロン
ランジャナ・ムコパディヤーヤ准教授
「日本の社会参加仏教 」

まずは ランジャナ先生のエネルギーにあふれた熱のこもったお話ありがとうございました、また先生力作の書『日本に置ける社会参加仏教―法音寺と立正佼成会の社会活動と社会倫理―』に贈られた二つの賞の受賞おめでとうございます。そして毎々マンデーサロン運営にあたられる諸先生,スタッフの皆さんご苦労様です。マンデーサロンは私にとりましては、浅学を少しでも補うべく、絶好の機会と思い積極的に参加させて頂いております。前期は残念ながら、授業の関係で出席させていただくことができませんでしたが、後期はまた末席をけがさせていただきたいと思っております。
当日のサロンの内容である「社会参加仏教」についてでありますが、今私の研究テーマであります18世紀ヨーロッパの寛容思想とも少々関連あるテーマであり、興味深く聞かせていただきました。当日別所先生からも質問がありましたが、国家の義務としての福祉政策と宗教団体の慈善活動との関係をどのように理解していくのか? また教義の実践なのか?単なる道徳的意味合いから来る社会的弱者救済活動なのか?宣教活動が本当に裏側にはないのか? などまだすっきり理解できないところもあります。 近代民主主義国家において、普遍的思想に位置付けられる「政教分離」思想、またフランス国家の「(宗)教・教(育)分離」政策などと考え合わせ、宗教団体の持つ社会的パワーが無視できない強さがある限り今後深く検討しなければならないテーマと感じました。
最後にランジャナ先生への直感的質問で申し訳ありませんが、エンゲイジド・ブッディズムにおきましては、救済活動の対象者となる社会的弱者の出現原因、救済活動などの対処的なものでなく原因解決などはどのように捉えているのでしょうか?
服部篤睦(博士前期課程院生)
第5回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年10月21日(日) 午後3時〜5時、栄の丸善4階、喫茶「カフェ・グラシュー」にて
テーマ: 「詩人BENNの”詩と真実” −1933年のナチ加担について」
講師:森田 明(人間文化研究科教授)
最初にコーヒーとケーキ・フルーツが運ばれ、司会者の講師紹介があり、本日のテーマ「1930年代のドイツの文化―異色の詩人ゴットフリート・ベン」について講義(というよりも分かりやすいお話)が始まった。
詩人ベンへの熱い思いを込めたお話が進むに連れて、まさにドイツ語で言うゲミュートリッヒカイト(Gemiitlich Keit)(くつろぎ・安らぎ)の雰囲気が漂う。文学でも門学・美術でも芸術家の作品は、その人の気質・性格、あるいは生い立ち・環境の影響を大きく受ける。エピソードを多く交えながら、詩人ベンの各作品とその背景が語られる。詩そのものよりも、まずこの詩人への関心が高まり、あとで具体的に彼の詩を読んでみようという気持ちにさせられる。ハイネ・ミラー・リルケらの抒情的詩人とは全く異なり表現主義的詩人と言われるベンについて、これは難解な話になるのでは、とはじめは予想していた。しかし、彼の作品に直接接したいという意欲がわき起こるのは、この催しに参加した意義を痛切に感じる。2時間でもまだ足りない。もっと参加者の質問・対話・議論の時間があるとさらに楽しいものになっただろう。
この催しも「市民学びの会」のどんな催しも、先生たちの研究内容を聴くだけでなく、自由な討議や交流がなされることも重要であろう。いずれにしても社会に開かれた大学として名古屋市立大学の益々の発展を願ってやみません。(寺岡信之)
第9回 マンデーサロン
2007年10月
福吉勝男(人間文化研究科教授)
「<ドイツ国制の近代的改革とヘーゲル>、そしてベルリンの今」
10月のマンデーサロンは、福吉勝男教授の「今日のヘーゲル研究とベルリン訪問」がテーマであった。
今回のベルリン訪問は氏にとって1994年の国際学会に参加以来の13年ぶりであったとのこと。ドイツの変貌、とりわけ東西ドイツの融合が進む中で、ベルリンの壁のみならず、生活の上でも制度の上でも壁が撤去され、融和が進んでいる状況が語られた。そのお陰で、今回の訪問の目的であったヘーゲル研究のための資料収集がとてもスムーズに行えたと言う。ドイツはいい方向に向かっているというのが氏の感想だった。
さて、今回の資料収集は「ヘーゲル国家論の謎」の解明のためだった。ヘーゲルの国家論は『法哲学講義要綱』に書かれているが、そこには謎が存在するのである。市民が市民の自覚をもって社会を形成し、その市民が市民社会を豊かに発展させるために国家を展望する姿と、それにふさわしい国家のあり方(機構・制度)を述べると言いながら、その国家論には不可解な点があって、市民の自治的・自主的活動の姿を「市民社会」論において最高に示しながら、「国政」論ではそれにふさわしいものとはせず、むしろこれに先立つ彼の国家理解から後退しているのである。この謎である。
この謎はどうして生じたのだろうか。現代のところは、政治反動を目の当たりにしてヘーゲルが自己規制をしたと推定されている。しかしこの推定は正しいのだろうか。今回のドイツ訪問は、ヘーゲルがベルリン大学の総長としてプロイセン改革に協力した相手の宰相のシュタインやハルテンベルクの国家改革構想の見解との対比で、この謎に迫ってみようということでなされたわけである。
シュタインのものでは、1807年9月の「ナッサウ覚書」、1807年10月の「10月勅令」、1808年11月の「都市条例」を、ハルデンベルクのものでは、1807年9月の「リガ覚書」を入手することが出来たと言う。翻訳をしてこの謎解明に努力したいとのこと。期待しよう。
久田健吉(研究員)
第4回 Human & Social サイエンス・カフェ
2007年9月16日(日) 午後3時-5時、栄の丸善4階、喫茶「カフェ・グラシュー」にて
テーマ: 「ポテンコ?の言語学―ソシュール生誕150年によせて」
講師:
成田徹男教授(人間文化研究科教授)

 会場である丸善の4階カフェに入っていくと、初秋にふさわしいシックなスタンドカラーシャツの成田教授が、熱心に資料を準備されているところでした。今回の配布資料は図を取り入れ、ソシュールのプロフィールから、「記号の原理」、「外来語らしさ」まで合計8ページにもわたる豊富な内容です。配られた参加者も大満足のようでした。ケーキと珈琲と配布資料とで、テーブルはいっぱいになりました。
会場である丸善の4階カフェに入っていくと、初秋にふさわしいシックなスタンドカラーシャツの成田教授が、熱心に資料を準備されているところでした。今回の配布資料は図を取り入れ、ソシュールのプロフィールから、「記号の原理」、「外来語らしさ」まで合計8ページにもわたる豊富な内容です。配られた参加者も大満足のようでした。ケーキと珈琲と配布資料とで、テーブルはいっぱいになりました。
先生から、先ずソシュールの生涯、続いてソシュールに関する文献紹介、「記号」、「恣意性」、「外来語」に関するお話がありました。フェルディナンド・ソシュール(1857−1913)は、スイスのジュネーブで生まれた言語学者です。55歳で亡くなりました。成田先生は今年、ちょうどソシュールが亡くなった年齢と同じ「55歳」になられたことを、聴衆に暴露されました。客席から「どよめき」が起こりました。参加者の皆さんが成田先生は、もっと「若い」と思っていたようです。これが、先生と参加者が打ち解けあった瞬間でした。私は成田先生のこのような話の導入に魅了されました。「話のイントロで客の心をつかむこと」が大切であることを実感しました。会場は、これで一気に和やかムードになり、最後まで気楽な雰囲気が続きました。
今年2007年は、ソシュール生誕150年ということもあり、日本語学の刊行物でも特集が組まれています。本日のサイエンス・カフェの論題は、そういう意味でもタイムリーな好企画でした。
ソシュールの著書ではありませんが、1906年から1911年にかけて、合計3回ジュネーブ大学で行なった講義を、後に受講学生たちがまとめ、世に出した『一般言語学講義(1916)』は、言語学を学ぶ者の間では、大変有名です。数年前になりますが、私は授業以外でも、この本を読んだことがあり、「記号」、「恣意性」、「構造」という3つのことばを思い出しました。
ソシュールは、言語が記号の1種であり、言語を構成する要素は体系をなすこと、要素の配列は一定の構造を形成することなどの、言語に関する特質を指摘しました。それらのことを、誰にもわかるように成田先生は身近な話題に結びつけて、やさしく解説されました。
さて、いよいよ、ここからが成田先生ならではの「ポテンコ」のお話です。本日の講演タイトルでもあります。「ポテンコ」という語形から判断して、「外国からきたことば」と感じる日本語話者が多いのでは?という先生の問いかけに、うなずく参加者が多かったです。私たちは、語の形から語種(和語、漢語、外来語)を推定するようなことがあります。実は、「ポテンコ」は、成田先生がことばの本質について語るとき、よく例に出される先生の造語なのです。 「ワンワンほえる動物」のことを「イヌ」と呼んでいますが、それでは、「ワンワンほえる動物」を「ポテンコ」と呼んではいけないでしょうかと、先生はさらに問いかけます。 たとえば、私一人が、「ワンワンほえる動物」のことを「ポテンコ」と言っても、ワンワンほえる動物の「イヌ」とは、他人は絶対に思いません。しかし、ある集団で申し合わせれば、「ワンワンほえる動物」を「ポテンコ」と言っても通じるようになります。伝達しあう人同士のあいだでわかればよいからです。このように、ソシュールのいう「恣意性」に関して、成田先生は少しずつ、その謎を解いていきます。恣意性があるからこそ、言語は地域や時代によって変化するということも教えていただきました。しかし、現実には社会性をも併せ持っているので、勝手に変えることはできないことを、先生は例示され丁寧に説明されました。
先生のお話の最中にも、客席から活発な発言や質問がありました。「言語」にこんなにも熱くなれるなんて、どういう人たちなのだろうかと、私は興味を持ちました。参加者の年齢は推測するところ、20代から70代、職業は学生、主婦、会社員など多様です。先生の眼前で、「ことば」についての持論を展開する熱心で意欲的な参加者に驚きました。 成田教授の声は、ソフトで穏やかです。やさしい雰囲気がよかったと参加者からも好評でした。お話のあいだ、目をつぶると1900年初頭のジュネーブ大学、口ひげをはやしたソシュールの丹精な顔(写真で有名)と受講学生たちのきらきら輝く瞳が目に浮かんできました。 講演が終了すると、「最後に、やっとポテンコの意味がわかってすっきりしました」と言って帰られる参加者がありました。講演のタイトルに付いた「ポテンコ」ということばが、ずっと気になっていた参加者も多かったようです。
サイエンス・カフェは、先生と参加者が距離感なく、同じ目線でディスカッションできるところがすばらしいと思いました。私も、「今日の参加者の皆さんのように、いつまでも熱く、意欲的に生きたい」と発奮する機会を得られたことを幸せに思います。ことばを通して交流することができ、これこそ、今日の論題にふさわしい最大の成果ではないかと感じました。
山田陽子(人間文化研究科博士後期課程)
第3回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年28月19日(日) 午後3時-5時、栄の丸善4階、喫茶「カフェ・グラシュー」にて
テーマ: 「沖縄の祭りと芸能」
講師:
阪井芳貴教授(人間文化研究科教授)

 日本各地で記録的な猛暑がTVニュースを賑わす8月19日に開催された阪井先生による「沖縄の祭りと芸能」も気温に負けない位の熱気を帯びていました。参加者の年代も南沙織の年代から安室奈美恵の年代と幅広く、当然、参加者の沖縄への関心事もさまざまで、最後の質疑応答を拝聴すると歴史、文化、親族形態、戦争問題などな多岐にわたっていたようでした。それをまとめる先生はさぞかしご苦労されたことでしょう。
日本各地で記録的な猛暑がTVニュースを賑わす8月19日に開催された阪井先生による「沖縄の祭りと芸能」も気温に負けない位の熱気を帯びていました。参加者の年代も南沙織の年代から安室奈美恵の年代と幅広く、当然、参加者の沖縄への関心事もさまざまで、最後の質疑応答を拝聴すると歴史、文化、親族形態、戦争問題などな多岐にわたっていたようでした。それをまとめる先生はさぞかしご苦労されたことでしょう。
今回はお盆明けということも考慮してかどうかは定かではありませんが、沖縄の神様を中心としたお話を、石垣島の「アンガマー」や沖縄の各地にある「御嶽(ウタキ)」などを例に挙げて分かりやすく解説していただきました。
沖縄県が観光立県となり、最近、沖縄には「青い海と異国情緒漂う楽園」といったイメージが定着してきていますが、現実は自然災害との戦いを独自の信仰観や祖先観で地域と助け合いながら生活してきた歴史が沖縄にはあります。日常生活において沖縄の特徴とはなんでしょうか?それは神や祖先との距離感だと思います。そのような特異性が柳田國男以来、数多くの民俗学者や人類学者の興味を引き付けて止まないところでしょう。沖縄の生活の基本となる家族や村落の中心に神があり、祖先があるということは観光地化された現在でも一歩踏み込んで沖縄を観察するとみえてきます。本土の都会に過ごす人々が日常に神や祖先を感じることがあるでしょうか。せいぜい「困った時の神頼み」程度の距離感なのではないかと思いますが、沖縄はちょっと違います。距離感の近さを裏付ける事例に沖縄における芸能の位置付けがあると思います。本来の芸能は神に対しての奉納であり、観客の存在は重要ではありません。沖縄は神と芸能と民衆が一体化しており、極端なことを言えば、祭事には村人全てが芸能者となり「カチャーシ」をしながら参加します。沖縄の人にとって祭事はきわめて身・u梛゜で、神と人、もしくは祖先と子孫のコミュニケーションであるといえるのではないでしょうか。
今回のサイエンス・カフェは美ら島沖縄大使でもある阪井先生が「神の島・沖縄」 への旅の楽しみ方の提案でもあり、商業主義的な祭りが増加する現在において「祭り」の原点を見つめ直す意味も含めて有意義でした。
唐木健仁(愛知県立大学大学院修士課程2年)
第2回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年7月22日(日) 午後3時-5時、栄の丸善4階、喫茶「カフェ・グラシュー」にて
テーマ: 「大人になるってどういうこと?―大学生への調査結果から問題に迫る―」
講師:
後藤宗理教授(人間文化研究科教授)

高校二年、まさに揺れ動く思春期の娘と一緒に参加しました。 人が生まれ、乳・幼児期、学童期〜を経て老年期に至る大きな流れの中で、それぞれの段階において何を獲得し得るのか、またはできないでいるのかという、エリクソンの話は年ばかりかさんでしまって中身が伴わず、なかなか大人になりきれない私には大変興味深いものでした。せめて、私の人生も、まあよかったんじゃないの!と思えるように、これからの時を過ごしていきたいとしみじみ感じました。
卒業してから二十年余りがたち、久し振りに聴く後藤先生の話は眠りかけていた何かをチクチクと刺激し、日常の様々な悩みを温かく包み込んで下さいました。現代の大学生の実態を伺って、私も決して良い学生ではなかったなぁと。ただ二十年以上がたち、同じ先生の話がこんなにも心の深い所に響いてきて胸にストンと落ちたり、共感できるようになったのは、ただ何となく過ごしてきたと思っていた年月の中で私が出会った人々や、経験してきた事などが少なからず影響しているのではないでしょうか?
(古田みぎわ)
今回の講演では、大学生の話を中心としたものだったので、今の私にはまだ共感できない部分があったものの、現在の大学生の実態を知ることもでき、これから進路を決めていく上でとても参考となるお話でした。
(古田祐理乃)
第1回Human & Social サイエンス・カフェ
2007年6月17日(日)3時〜5時、栄の丸善4階、喫茶「カフェ・グラシュー」にて
テーマ:「戦国時代武将の文化活動−『月庵酔醒記』をとおして」
講演:服部幸造(名古屋市立大学・人間文化研究科・教授)

記念すべき第一回目は服部幸造先生の「戦国時代武将の文化活動」がテーマでした。今川了俊、太田道灌ら私も名前ぐらいは知っている武将たちが「文化人」としてはどんなことをしていたか、というような紹介があったのち、三河の国に出自の由来を持つ一式直朝(月庵)〜のちに、幸手(さって:現在の埼玉県内)城主〜というサムライが著した『月庵酔醒記』の話しに入りました。
この本は、一般の人間はもちろん、中世文学の研究者でもほとんど知られていない、読まれていない、読むのも難しく読んでもよくわからない、というないないづくしの書のようです。それをこのほど服部先生が注釈本として出版しました。もとはさほど長くないけれども、注釈にスペースを要して3巻本となる予定で、この4月にその上巻が出たばかりだそうです。誰もしてこなかった仕事だということで、6500円にもかかわらず割とよく売れているとのこと。

この書物は月庵さんが読んだり聞いたりしたというネタの、聞き書き抜き書きがほとんどで、著者のオリジナルなものなどほとんどない!、しかもくだらない内容ばかりだ!と服部先生はこっぴどくこきおろしながらも、当時(16世紀前半から末葉)の文化万般、すなわち芸能、俳諧などにはじまり、医術、武術や巷間説話などまで、ありとあらゆるジャンルについて網羅されているという意味では、文化の担い手だった公家・貴族たちの生活、風俗、遊びなどが活写されていること、そしてどちらかというとやんごとなき人々の文化の権威性が引き剥がされつつ、上から下へ、京から東国へと文化が伝えられていると解釈できそうだと解説されました。(いささか私流理解も混じっているかもしれませんので、ご注意を。)
服部先生の軽妙洒脱な語り口にもかかわらず、はじめのうちはやや硬い雰囲気もありましたが、一つふたつ質問がでるに及び、急速にサロンムードが高まり、質問や感想・意見が飛び交って、服部先生も適宜とぼけて下さるので、たいへんなごやかな空気につつまれるようになりました。
参加者は、19名。講師を含めて募集数の20名ジャストでちょっと少ないかなとも思われますが、規模的にはちょうどよい感じでした。それでも声が届きにくいという意見もあり、次回からは店側にマイクアンプを用意してもらえそうです。
人間文化研究科教授 有賀克明
第8回マンデーサロン
「ダム問題の社会学―変わる社会認識と変わらない問題構造、そして、新たな上下流間関係の模索へ―」浜本篤史講師(環境社会学)(2007年6月11日)
今回のマンデーサロンは、本学に今年度着任されたばかりの浜本篤史講師(環境社会学)のご報告であった。フレッシュな先生のサロン登場とあって、早くから注目を集めていた。「ダム問題の社会学―変わる社会認識と変わらない問題構造、そして、新たな上下流間関係の模索へ―」と題して、ダム調査歴、ダム建設の概要、ダム問題の構成と問題構造、住民の位置関係、課題等をお話しいただいた。
浜本先生は1990年代後半から日本各地のダムや中国の三峡ダムを調査研究されている。本サロンではパワーポイントを使用して、ダム建設の現場写真や図表をもとに、ダム問題をわかりやすく丁寧に説明された。写真の中でも「旧徳山小学校」の落書き写真や「徳山ダムの建設中止を求める会」の写真が印象に残った。日本はダムの建設数が2,759にのぼり、世界でトップ5に入る「ダム王国」であるとのお話にも驚いた。
佐久間ダム(1956年完成)や黒部ダム(1963年完成)に代表されるように1950年代から60年代はダム建設の黄金時代であった。しかし、1990年代半ば頃からは「無駄な公共事業」として社会的批判を受けるようになったという。浜本先生は、私たちの記憶にも新しい2001年の長野県知事「脱ダム宣言」、2006年の滋賀県知事「ダム凍結宣言」などの例を示され、具体的にダム建設が冬の時代に突入したことを説明された。その背景には水需要の伸び悩み、治水効果への疑問、生態環境への影響、政・官・財の癒着構造による国民の不信感等がある。
また、ダム問題は局地的対立構造(事業者対予定地住民)から社会的に広域な展開(下流地域住民もその構造に参入)へと変化してきた。
浜本先生のお話で興味深かったのは、ダム計画をめぐる社会問題の変容と予定地住民との関係性であった。確かにダム計画をめぐっては、戦後直後から今日まで、社会問題の性格は変容している。しかし、たとえ「開発の時代」であっても「環境の時代」であっても変わらないのは、「水没予定住民」という犠牲者の存在が一貫して軽視されているということである。 住民が経験した精神被害やアイデンティティの問題も興味深かった。ダム事業というのは最低でも数年がかり、長期化すれば数十年かかる。住民との交渉・建設工事の遅延による事業の長期化が原因で、住民の中には「一体自分はこの何十年、何をしていたのか。自分は何をやっていたのか。」と「自分」の存在がわからなくなる人や精神が破綻する人もいるという。このほか家族問題の発生もあり、水没予定地にとっての現実経験は深刻である。今回のご報告から、ダムの公共性とは何かを考えさせられるとともに「公共事業は、犠牲となる水没地への配慮が必要である」ことを教えられた。
浜本先生は落ち着いた、爽やかなトークで、聴衆を魅了した。機会があれば中国の三峡ダムについてもお話を伺いたいと思う。環境社会学という学問を身近に感じた今回のサロンであった。
人間文化研究科博士後期課程生 山田陽子
第7回 マンデー・サロン
「抑うつ的音楽聴取に伴う気分の変化―抑うつ傾向と聴取音楽に対する好みの検討―」古賀弘之教授 (2007年5月14日)
毎回入れかわり立ちかわり先生方から、全くの門外漢にもわかりやすく、それぞれのご専門の話を聞かせてもらえるマンデーサロンには、第一回から私はほとんど毎回参加させてもらっている。今回も気楽に参加したら、福吉先生から感想文を書くよう依頼されてしまったので、つたない文ではあるが敢えてここに感想を述べることとする。
今回は昨年度と大きく違ったことが二つあって、そのひとつは会場が広くなったことと、もうひとつは参加者の顔ぶれが一変したことであった。昨年度は人間文化研究所で、いつもお茶を飲みながら、サロンそのものアットホームでな雰囲気で行なわれていた。しかし本年度は広い会議室で開催され、参加者も増えた。というより参加者が多いと予測されていたから広い会議室でということであろうか。
実際確かに参加者は昨年度より多かったが、その顔ぶれは一変していた。それは一般市民とおぼしき方々の参加が多く、先生方の顔ぶれが昨年までとは少し違っていた。昨年常連だった多くの先生方のお顔がなく、ちょっとさびしかったし院生の参加が私一人だけだったのはもっとさびしかった。私はこの変化がよいとか悪いとか言える立場ではないのでコメントは差し控えるが、マンネリ化を嫌い、よりよいマンデーサロンにしようと努力されている先生方にはエールを送りたい。
つぎに今回の講演の内容について述べると、私の知的好奇心をおおいに満たしてくれた。もちろん私は音楽療法については全くの門外漢ではあるが、音楽は大好きである。好んで聞くのはクラシックで、作詞・作曲にも興味があり、自作曲を自分のホームページで公開したり、CDアルバムも自作したりしている。また、以前民間会社の研究室に勤務していたとき、QC(品質管理)活動の一環として不良製品の原因究明のため、分散分析や実験計画法を手がけたことがあった。つまり不良品の原因は作業者か、装置か、原材料か、など多数の因子が考えられる場合、ラテン方格を組んで実験計画を立てたりした。
本講演は学生がクラシック音楽を聴くことにより、どのように気分変化するのか、という内容であり、その手法として分散分析を使われたということが興味深かった。
最後に、かなり初歩的でしかも無遠慮な質問にもかかわらず、親切丁寧にお教えくださった発表者古賀先生に改めて感謝してペンを置く。
大学院博士前期課程生 岩瀬彰孝
第6回 マンデー・サロン
「外国人労働者受け入れの日本型モデルを求めて
〜少子高齢化と人口減少社会にどう対処すべきか〜」村井忠政教授 (2007年2月5日)
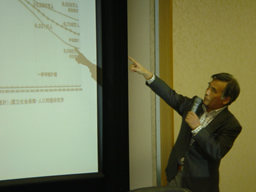

2月5日、この二年間人間文化研究所の所長をお務めいただいた、村井忠政先生最後のマンデー・サロンが開催された。いつもとは異なり、場所を大会議室に移して、OHPを使っての講演が始まった。時折ユーモアを交えながら、多文化共生についての最新の研究動向が非常にわかりやすく紹介されていく。さすが!
タイトルは、「外国人労働者受け入れの日本型モデルを求めて〜少子高齢化と人口減少社会にどう対処すべきか〜」という、わが国にとっての喫緊の課題だ。しかし、このタイトルとは打って変わって、村井先生は外国人労働者の安易な受け入れに反対のようだ。それは、経済的理由を優先することによる負の側面として、解決しがたい人権問題がつきまとうからである。多文化共生の課題は人権問題であるという主張が幾度となく繰り返された。そして、過酷な生活を余儀なくされる外国人労働者の子どもたちが、十分な教育を受けられるようにする必要性があるとの言に力がこもった。ここには、先生が多文化共生にかける想いがよく現れている。「いまここにある危機」としての多文化共生という課題。その克服こそが将来の外国人労働者受け入れの試金石だということなのだろう。少なくとも私はそのように理解した。
もう間もなく村井先生は名古屋市立大学を去られる。しかし、村井忠政氏個人のプロジェクトは始まったばかりである。あの人懐っこくも鋭い目が、僕たちにそう語りかけていた・・・。
人間文化研究科博士後期課程 小川仁志
第5回 マンデー・サロン
India-China-Japan Cooperation and the New Strategic Balance in Asia」
「インド・中国・日本間の協力とアジアにおける新たな戦略バランス」
Visiting Professor, Baladas Ghoshal バラダース・ゴシャール客員教
(2006年12月4日)

12月4日に開催されたマンデー・サロンは、本大学人文社会学部客員教授であるインドのジャワハルラル・ネルー大学のバラダース・ゴシャール教授による、アジア国際関係における新秩序形成の可能性についての講演であった。すでに経済大国である日本に加え、近年経済成長がめざましい中国、そして近年IT革命で注目されるインド、これら三国が一億を超える人口、そしてGDPやPPP(購買力評価)の額からもアジアの三大巨人といえ、これら三国が経済・商業的に密接に連携するだけでなく、外交・軍事・安全保障上でも協力関係を築くことが、アジアのさらなる繁栄と地域の安定、さらには平和の構築に貢献するという主張であった。
中国とインドは、実はごく最近まで約40年間にわたる国境紛争による対立関係にあったが、約二年前に両国の経済協力関係を踏まえて敵対関係にようやく終止符を打ったばかりである。日本と中国の関係も、安倍首相による中国訪問、北朝鮮問題をめぐる日中の多少なりの協力関係など、小泉内閣時代に比べると、少しながらも改善の兆しをみせはじめている。また日本企業によるインドへの積極的投資など、三国間の距離は縮まりつつまることも、ゴシャール教授の主張に現実味を持たせている。これら三国以外にも、韓国やASEAN諸国との協力などの地域連携が、米国主体の安全保障体制から地域主体の安全保障体制へと移行する可能性を示唆した。
これに対して経済・商業分野での三国の協力関係はいいとしても、安全保障問題については、日米安全保障条約やASEAN諸国の米国への安全保障上の依存、台湾問題、中国とインドが核保有国であるが日本は非核国である点、三国による大国主義に陥ることへの懸念などの質問・批判が出されて、活発な議論が行われた。
日本の対アジア外交のさらなる改善の必要性を強く感じるとともに、アジアの国際関係をインドなどの南アジアからと、日本からの視点では、異なる見方が可能であることがわかり、こうした視点の違いによって学問的考察を深める貴重な機会となった。
人間文化研究科 助教授 松本佐保
第4回 マンデー・サロン
「日露戦争と黄禍論の言説――日英関係における人種問題をめぐって――」
松本佐保助教授 (2006年11月6日)
 11月6日に開催されたマンデー・サロンは、黄禍論についてであった。私にとって、興味深かったのは、日英関係における人種問題を日露戦争の経過とイギリスの国際的状況から発表された点であった。
11月6日に開催されたマンデー・サロンは、黄禍論についてであった。私にとって、興味深かったのは、日英関係における人種問題を日露戦争の経過とイギリスの国際的状況から発表された点であった。
私は以前から人種差別問題に興味があり、黄禍論に興味を持っていた。ドイツ皇帝Wilhelm2世が「黄禍」を広めたといわれているが、実際には彼は下絵を描き、宮廷画家にあの有名な絵(1895)を描かせた。そのタイトルには、「黄禍」という語はなかった。“yellow peril”という言葉はアメリカで生み出されたという文献も読んだことがあるが、はっきりしないようである。その語の発生はともかく、「黄禍」というスローガンが与えた影響は大きく、容易にアジア系アメリカ移民は差別の対象となった。イギリスでは1822年に、リチャード・マーチン議員の活動により、「畜獣の虐待および不当な取扱いを防止する法律(マーチン法)」が成立した。ウマ、ロバ、ラバなどがその法律の対象とされた。しかし、イギリスは植民地において、人間を畜獣以下に取り扱った。アメリカで、マジョリティであったイギリス系アメリカ人は奴隷制度を長期に渡り実施し、アジア系移民を安い労働力として特に危険な作業に従事させ、今日の発展を遂げた。畜獣を保護する一方で、人間を搾取していた当時のイギリス系の人々をどのように理解したらいいのであろうか。
9・11以降、「宗教の違い」がクローズアップされている。宗教の違いは確かにあるであろう。しかし、secularな私は、経済的や政治的な要因が様々な問題を大きくしていると感じている。古代から、人間は未知なものに対し恐怖心や羨望を抱き、学者や時の指導者は何らかのスローガンを打ち出してきた。一旦生まれたスローガンやステレオタイプ的観点は一人歩きして、想像も出来ない方向に向かうこともある。たとえ、そのスローガンが国際的に否定されても人々の心の中には残像が存在する。今は情報源が多岐に渡っているが、判断するのは人間である。「黄禍論」研究はテロ対策、北朝鮮(DPRK)問題にも関与する研究であると感じた。発表者である松本先生の博士論文のテーマは19世紀の宗教と国際問題とのこと、次回は宗教の観点からのお話を伺いたいと思いました。
人文社会学部研究員 房岡光子
第3回 マンデー・サロン
「古代の民衆像を再考する」吉田一彦教授 (2006年10月2日)
「古代の民衆像を再考する」

月に一度、第1月曜日に開催される「マンデーサロン」も3回目となった。今回は吉田一彦教授を講師に「古代の民衆像を再考する」と題しての講義である。「民衆の古代史―『日本霊異記』に見るもう一つの古代」のタイトルで、著書が風媒社から刊行されたのはこの4月のこと。「ストレスがたまると原稿が進むんですよ」という教授の話は、「日本霊異記」から始まった。遭難した漁民、勝手に出家した私度僧、強欲な金貸しなど市井に生きる人々の暮らしぶりが生きいきと描かれている日本最古の仏教説話集である。かつてはただのものがたりだと思われていたこれらだが、幾多の木簡の出土や遺跡の発掘によって、信頼に足る史料だと吉田教授は確信したという。「山川出版の日本史にはたしか『律令国家の成立』という章立てがありますよね」との問いかけに深く頷く参加者たち。
「律令国家」とは、古代国家の一形態で、律令を統治の基本法典としたもの。巨大な官人群を擁し、人民に班田収受によって一定面積の耕地を保障する代わりに、戸籍につけて租・庸・調・雑徭など物納租税や徭役労働を課し、個別人身支配を徹底した。日本では隋・唐に習って7世紀半ばから形成され、奈良時代を最盛期とし、平安初期の10世紀頃まで続いた。(広辞苑より) 「日本霊異記」に記される古代社会の実態は、律令の定める国家の姿とは大きく異なっていることをどう説明したらよいのだろうかと教授は続ける。まずは古代国家が「法に基づく国家」なのかどうかを再考すべきであり、「法の支配ではなく、人(天皇)の支配に基づく国家」ではなかったかと吉田説が展開する。古代史パラダイムの転換である。
つい先日、島根で平安初期の「唐風女性像」の板絵が発掘された。千年以上も埋もれていたタイムカプセルからはどんなメッセージが読み解かれるのだろう。まったくの初心者の想像力をかくも刺激する、スリリングで贅沢な時間をいただいた。次回「マンデーサロン」の開催が待たれるところである。
人間文化研究科博士前期課程生 重原厚子
第2回 マンデー・サロン
「使えるヘーゲル」 福吉勝男教授 (2006年7月3日)

7月3日月曜日。第2回目の開催となった「マンデー・サロン」は、研究所の椅子が足りなくなるくらいの盛況ぶりであった。講師は福吉勝男教授。言わずと知れた、ヘーゲルをはじめとしたドイツ哲学の専門家である。つい最近平凡社新書より刊行された著書『使えるヘーゲル 社会のかたち、福祉の思想』について直々に話が聴けるとあって、多くの教員、院生らがこの本を片手に半ば興奮気味に集まってきた。
実際には、福吉教授の話はこの本の単なる内容紹介というよりも、それを今後さらに発展させ、展開するうえでのラフスケッチを示すことを中心に進められた。題して「現代の〈公共哲学〉とヘーゲル」。ヘーゲルの市民社会論に公共圏を見出し、現代の公共性をめぐる一連の議論、あるいはトクヴィル、アーレント、ハーバマスといった思想家のそれと比較を試みた興味深い内容である。「この発見が一体どう活かされるのか?」表現は様々であったものの、参加者からの質問はこの一点に集中したように思われる。
これに対して提示された答えは、「〈市場−公共〉リンク市民社会論」という全く新しい概念であった。その中身は明確には示されなかったが、誰もが自分の手でそれを探り出したくなるような誘惑にかられていたことだけはたしかである。ヘーゲルへの誘い。福吉教授の意図は実はそこにあったのかもしれない・・・。
人間研究科博士後期課程生 小川仁志
第1回 マンデー・サロン
「和泉式部の亡霊」 服部幸造教授 (2006年6月5日)

6月5日(月)に本学人間文化研究所にて、本研究科教授服部幸造氏による発表「和泉式部の亡霊」がなされた。参加者は本研究科教員・大学院生・修了者含め20名近くもあり、本研究科の規模と月曜日の夕方という状況を考えると第1回目の“マンデー・サロン”に大きな関心が寄せられていることが伺われよう。
氏の発表は、和泉式部がその生前のイメージから中世における“亡霊”概念と重ね合わせられ、一種の信仰として畏敬の念をもって語り継がれていく様を、応仁の乱前後から戦国末期あたりまでの古典芸能や各種記録類を通じて新資料をも踏まえながら明らかにしたものであり、古典文学や芸能を通じて日本文化の研究に長年の研鑽をつまれた氏の力量の確かさと学識の豊かさ、さらにはその巧みな話術もあいまって氏の講義が本学における“人気講義”であることを納得させるに十分な内容であった。質疑応答においては、日本仏教史についての基礎的な知識から、当時の信仰の実態にいたるまでと幅広いテーマが話題となった。
また、本研究科においてはいわゆる古典研究を専門とする教員は比較的少数であるが、氏の発表に他領域の教員・院生が触れることにより、古典研究の世界を垣間見ることができたのは有意義な点の一つであったと思われる。他領域間の、また公的私的なコミュニケーションの場としての“マンデー・サロン”のさらなる発展が望まれる所以である。
人間研究科博士後期課程生 原口耕一郎
「共生」シンポジウム
(2005年1月24日 山田明/記)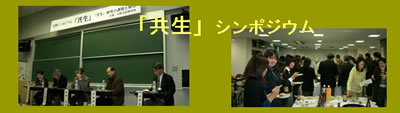
昨年12月18日に人文社会学部棟201教室で「共生」をテーマにした公開シンポジウムを開催した。主催は人間文化研究科であり、夏から準備してきた。こうした研究科主催のシンポジウムは、学部・研究科ができてから初めての企画である。かねてから学部・研究科の「存在」を対外的にアピールする必要を感じていたので、研究科長自らが「旗振り役」になって企画・準備してきた。
本研究科は法人化準備の過程で研究所設立、教職などの免許資格を重点課題と位置づけ、各方面に働きかけてきた。この4月には「人間文化研究所」が設立できることになり、その記念の催しにもすることができた。パネリストは今福龍太氏、平野健一郎氏、水野理恵氏、宮島喬の4氏であり、コーディネーターを村井忠政氏がつとめた。
パネリストの「顔ぶれ」もあり会場がほぼ満席になった。事前に参加者数が把握できなかったので、ほっとしたものである。シンポジウムでは「共生」研究の課題と展望をテーマにして、4時間半近くの報告と討論がなされ、密度の濃いシンポジウムになったと思う。この内容は報告書として刊行される予定だ。これから研究所を中心にして、「共生」「多文化共生」ないし「共生社会」研究を推進していきたい。
シンポジウムが終わってから「懇親会」を行った。これも「生協」食堂でやったこともあり「盛況」であった。


