著書・論文

[著書]
1 日本古代社会と仏教

吉川弘文館 1995年
6800円+税
著者の第一論文集。以下の九篇の論文を収める。
Ⅰ国家仏教論批判/Ⅱ僧尼令の運用と効力/
Ⅲ古代の私度僧について/Ⅳ行基と古代法/
Ⅴ行基と呪術/Ⅵ御斎会の研究/
Ⅶ寺と古代人/Ⅷ僧尼と古代人/Ⅸ日本古代の三宝
2 日本史の中の女性と仏教

法蔵館 1999年 2600円+税
西口順子、勝浦令子と共著。光華女子大学真宗文化研究所編
以下の六章からなる。
1女性と仏教をめぐる諸問題(吉田一彦)
2『日本霊異記』を題材に(吉田一彦)
3古代の尼と尼寺(勝浦令子)
4女性の出家と家族関係(勝浦令子)
5尼と「家」(西口順子)
6真宗史のなかの女性(西口順子)
3 蓮如方便法身尊像の研究
法蔵館 2002年(近刊)
脊古真哉、小島恵昭、岡村喜史、蒲池勢至と共著
同朋大学仏教文化研究所編
真宗では、本尊として阿弥陀如来の絵像をまつるが、これを方便法身尊像という。これには裏書が書かれ、重要な史料となっている。本書は、現存するすべての蓮如裏書、順如裏書の方便法身尊像を実見調査し、その写真を表裏とも大判のカラー写真で掲載し、あわせていくつかの論文を掲載するものである。
吉田担当の論文は、
「総説 本願寺流真宗と方便法身尊像(共著)」
「日本仏教史上の蓮如の位置」
「本願寺住持としての順如」
の三本。
[最近の論文]
1 多度神宮寺と神仏習合
(梅村喬編『古代王権と交流 4伊勢湾と古代の東海』所収)
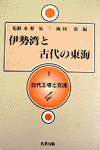
名著出版 1996年
日本古代の神仏習合は、中国の神仏習合とよく似ている。日本古代の神仏習合は、日本国内で形成された思想ではなく、中国から輸入し、これを受容したものであることを論じた。その導入には、道慈、最澄、空海などの入唐した僧が関わっていることも説いた。
2
僧旻の名について

(薗田香融編『日本仏教の史的展開』所収)
塙書房 1999年
大化改新の時に活躍した「僧旻」は、ふつう僧の旻であるとされているが、彼の名は実は、「僧旻」であることを説いた。そこから日本書紀の編纂過程や、道慈の関与についても言及した。
3 実如の継職と初期の実如裏書方便法身尊像

(『実如判五帖御文の研究 研究篇下』所収)
法蔵館 2000年 同朋大学仏教文化研究所編
4 日本書紀と道慈
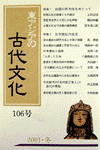
『東アジアの古代文化』106号
大和書房 2001年
『聖徳太子の実像と幻像』に再録
大和書房 2002年
5
『元興寺縁起』をめぐる諸問題――写本・研究史・問題点――

『古代』110号
早稲田大学考古学会 2001年

.gif)
|